精神科訪問看護の業務内容はきつい?対象疾患は?目的や訪問看護との違いを解説
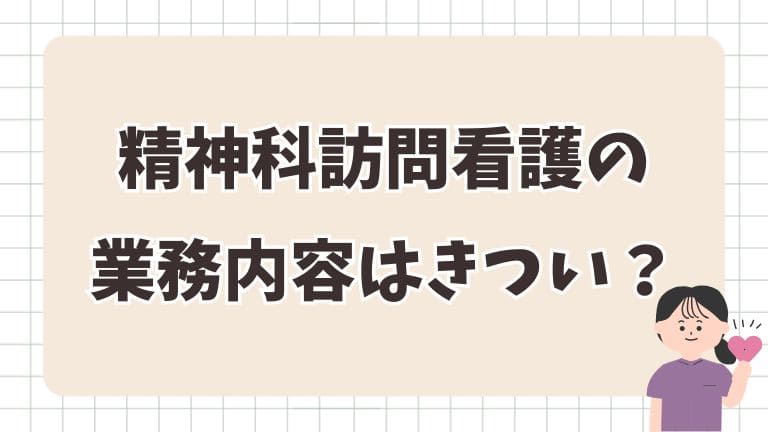

精神科訪問看護って普通の訪問看護とどう違うの?

精神科の訪問看護は大変って聞くけど、実際どうなんだろう?

精神科訪問看護って普通の訪問看護よりキツそうなイメージあるよね。
そんな疑問や不安を感じている方も多いかもしれません。
この記事では、精神科訪問看護の仕事内容や対象疾患、「きつい」と言われる理由や、実際に働く中で私が感じた対処法などをわかりやすく解説します。
精神科訪問看護師として数年間勤務してきた経験から、リアルな現場のエピソードや体験談も交えながらお届けします。
「自分にもできるかな?」
「どんな人に向いている仕事なんだろう?」
そんな思いがある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
自分に合った働き方のヒントが、きっと見つかるはずです。
精神科訪問看護とはどんなもの?
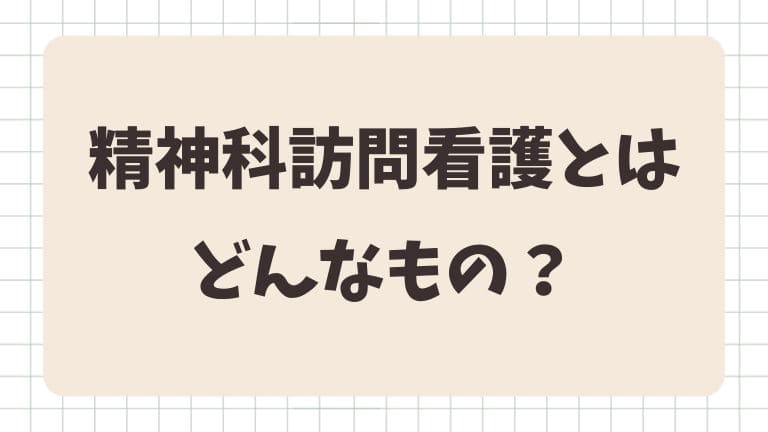
厚生労働省の資料では、精神科訪問看護とは下記のように定義されています。
精神科訪問看護は、精神障がいをもって地域で暮らす人の健康と生活を支え、利用者と家族のリカバリーを支援する医療サービスである。利用者数や実施施設数は年々増加しており、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」にも欠かせない支援となっている。
地域における支援ニーズの高いものに対する精神科訪問看護の実態調査報告書(厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業)
要するに、精神科訪問看護は、心の病気がある人が地域の中で安心して暮らしていけるように、医療やサポートを届けるサービスとして位置づけられることが多いです。
精神科訪問看護の目的は「再発予防」と「日常生活の安定」
精神科訪問看護の大きな目的は、症状の再発や悪化を防ぐこと。
その上で、利用者さんが安心して日常生活を送れるように支えるのが役割です。
「入院治療が終われば、あとは普通に暮らせるのでは?」
と思われるかもしれません。
でも実際は、退院してからが大変だったりします。
- 生活リズムを取り戻すのが難しい
- 周囲の人間関係に戸惑う
- ご家族がサポートに疲れてしまう
こんなふうに、退院後の生活ではいろんな壁にぶつかることが少なくありません。
精神科訪問看護は、そういった方々に対して、
- 日々の様子を見守る
- 不安や悩みを相談できる存在になる
- 小さな変化に早く気づく
そんな風に「日常の中で寄り添うケア」を提供することで、安心して生活を続けるための支えになります。
医療職が定期的に関わることで、症状の変化に早く気づける可能性が高まり、ご本人・ご家族にとって大きな安心材料になることもあります。
通常の訪問看護と精神科訪問看護との違いは?
精神科訪問看護は、「心の安定を支えること」が中心のケアです。
これは、身体のケアをメインとする通常の訪問看護との大きな違いになります。
訪問看護と聞くと、多くの人が「点滴やリハビリ」「身体のケア」をイメージするかもしれません。
実際、一般的な訪問看護は身体の病気や日常動作の回復サポートが中心です。
- 血圧管理
- 褥瘡予防
- カテーテル類や呼吸器管理
- リハビリ
- 服薬確認
- 入浴介助
など、医療と生活をつなぐ役割を担っています。
一方、精神科訪問看護の中心は心の安定を支えること。
- 利用者さんの気持ちに寄り添う
- 日々の変化を見守る
- コミュニケーションや対話そのものがケアになる
といった関わりが大切にされています。
例えば、

「ここ1週間は〇〇(利用者の困りごと)はどうでしたか?」
「なんとなく◯◯(疲れているよう、しんどそう)にも見えますが、無理していませんか?」
といった何気ない会話の中で、表情や声のトーンからその人の変化に気づくことも。
症状の変化を早めに察知できれば、必要な支援につなげるタイミングを逃さずに済むケースもあります。
もちろん、服薬の継続や生活習慣の維持をサポートすることもありますが、
“傾聴そのもの”が安心につながるのが精神科訪問看護ならではの特徴です。
精神科訪問看護は、「手を貸す」よりも「そばにいる」ことが何よりの支えになる場面が多い。
そんな看護の形だと実感しています。
精神科訪問看護の業務内容
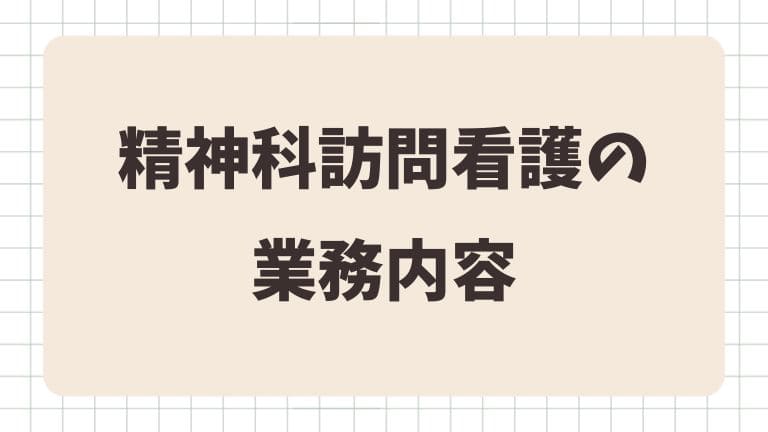
精神科訪問看護では、利用者さんの状態や生活状況に応じて、次のような支援を行うことがあります。主な業務内容が以下の5つです。
- バイタルサイン測定や精神状態の観察
- 服薬管理
- セルフケア・医療的ケア
- 家族へのサポート
- 地域の多職種と情報共有・連携
順番に見ていきましょう。
※必要な支援は人それぞれ異なるため、主治医の指示やご本人・ご家族の希望に沿って提供されます。
バイタルサイン測定や精神状態の観察
精神科訪問看護では、多くの利用者さんに対して、バイタルサインの測定や精神状態の観察をしていきます。
高齢で高血圧などの既往がある人も多く
「今日も問題ありませんね」
と伝えると、それだけで安心される場面も度々あります。
精神状態の観察では、
- 声のトーン
- 話す内容
- 服装・身だしなみ
- 生活のリズム
- ご家族の様子や支援の状況
なども含めて、その日の様子を丁寧に確認していきます。
例えば、お部屋がきれいに片付いていると「普段の生活はある程度保てているのかな」と思うこともあります。
ただ、それが幻聴の指示で片付けをしている場合もあるため、状況によっては注意して様子を見ていく必要があります。
幻覚や妄想の影響で、自分や周りの人を傷つけたりしている場合は、適切な介入が必要です。
訪問看護師だけで判断せず、主治医やケアマネジャーと相談しながら対応を考えることが大切になります。
服薬管理
服薬管理は、利用者さんの体調や理解度、ご家族の支援状況に応じて、看護師が個別ケースに合わせサポートします。
お薬を正しく続けていくことは、体調を安定させるうえで大切なポイントです。
でも、服薬の自己管理が難しい方や、支援が必要なご家庭もあります。
そのため、訪問看護ではご本人やご家族の状況に応じて、次のようなサポートを行うことがあります。
- 一緒に薬カレンダーに薬をセットする
- 利用者さんがセットしたものを看護師が確認する
- 看護師が全ての薬セットを代行する
支援の仕方はケースバイケースですが、共通して大切にしているのは
「できることはなるべくご本人にやってもらう」という視点です。
無理のない範囲で「自分でできる」経験を積んでもらえるよう、一人ひとりに合った関わり方を意識しています。
セルフケア・日常生活の援助
精神科訪問看護では、日常生活が安定して送れるよう、生活リズムやセルフケアの支援も行います。
こうした“生活のリズムを整える関わり”も、精神科訪問看護ならではの支援です。
清潔ケアとして以下のような支援を行うことがあります。
- 爪切りなどの身だしなみのサポート
- 必要に応じた清拭や足浴などのケア
ただし、清潔ケアの実施頻度はそれほど多くなく、実際の支援内容や方法は、
主治医の指示や事業所の方針、利用者さんの状態に応じて異なります。
たとえば、高齢の利用者さんで足の爪切りが難しいケースでは、対応できる範囲で支援することもあります。
こうした小さな関わりをきっかけに、信頼関係が深まる場面も度々あります。
なお、以下のような医療処置については、看護師の判断では実施できません。
あくまで医師の指示がある場合に限られます。
- 浣腸
- 褥瘡の処置
- 創傷処置 など
万が一訪問中に処置の必要があると判断した場合は、ステーション内のスタッフや主治医と連携しながら、対応方法を検討します。
(精神科訪問看護に必要な看護技術については別記事を執筆予定です)
家族へのサポート
精神科訪問看護では、本人だけでなく、ご家族の気持ちに寄り添うことも大切な役割です。
訪問中、ご家族が同席される場合もよくあります。
その時に大事なのは、「ご家族の様子や気持ち」にもきちんと目を向けることです。
例えば、実際に訪問していると以下のように感じる場合も多い傾向です。
- ご家族が安心して過ごせていると、利用者さんにもその空気が伝わる
- 逆に、ご家族が疲れ切ってたら、利用者さんも落ち着きにくくなる
ご家族から相談を受ける際は、まずはしっかり話を受け止める姿勢を大切にしています。
その上で、必要があれば主治医やケアマネと連携して、一緒に対応を考えていきます。
「誰かに話せてよかった」と思ってもらえるように、寄り添うことが大切です。
地域の多職種と情報共有・連携
精神科訪問看護では、地域全体の多職種と連携することも多いです。
さまざまな関係職員と連絡を取り、相談や調整を行うのは、病棟看護師との大きな違い。
例えば、利用者さんの支援に関わる場面では、こんな人たちとやり取りすることがあります。
- ケアマネージャー
- 地域包括センターの職員
- 地域の保健師
- 施設職員(グループホームなど施設入所中の利用者さんの場合)
- 主治医 など
病棟でも他職種連携はありますが、訪問では「地域のつながり」がさらに広がる感じです。
病棟のチーム医療とはまた違う職種との連携のため、とても勉強になることばかり。
地域でさまざまな立場の方と一緒に利用者さんを支えていくのは、訪問看護ならではのやりがいです。
精神科訪問看護の対象疾患は?
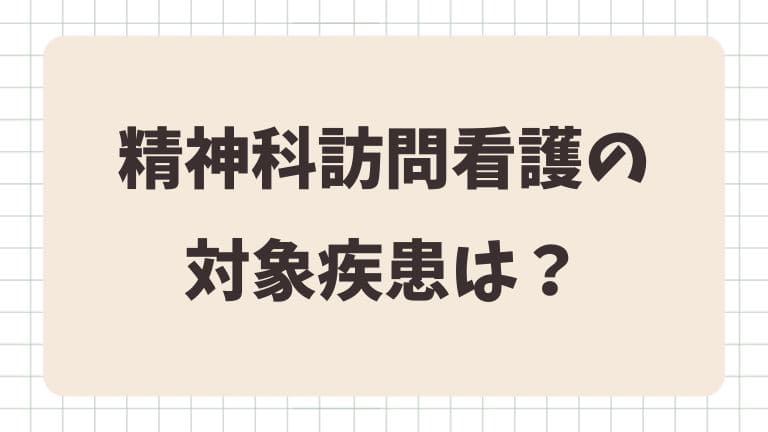
精神科訪問看護では、主治医の指示のもと、さまざまな精神疾患を抱える方のサポートに関わることがあります。
ここでは、現場でよく出会う代表的な疾患の一例を紹介します。
※ただし、これはあくまで訪問看護の現場で関わることの多い病名の例であり、診断や治療を目的としたものではありません。
気になることがあれば主治医や専門職に相談してみてください。
統合失調症
精神科訪問看護では、統合失調症の方と関わる機会が多い印象です。
幻覚や妄想によって、生活のペースが乱れやすい方もいらっしゃるため、訪問ではこんなことを一緒に確認する場面があります
- お薬はきちんと飲めているか
- この1週間どんなふうに過ごしていたか
- 今、困っていることや気になっていることがあるか
とはいえ、毎回かっちり質問するというより、
日常の会話やちょっとしたやりとりの中から、その人の変化を見ていくようにしています。
例えば、
- 表情の明るさ
- 話し方のトーン
- 部屋の様子や雰囲気
など、小さな変化に気づけるよう、対話の中で“無理なく”引き出す工夫をすることが多いです。
中には、「あんまり根掘り葉掘り聞かれるのは苦手…」という方も。
だからこそ、まずは信頼関係を築くところから始まるのが、この支援の特徴かなと感じます。
うつ病や双極性障害など
うつ病や双極性障害の方では、気分の波に合わせて、日々の様子が大きく変わる場合もあります。
その日の気分や体調によって、話し方や反応が変わる場面もよくあります。
例えば、以下のような感じです。
- 「最近ちょっと調子いいんですよ」と笑顔で話してくれる日
- 声をかけても返事がほとんどない日
だからこそ、訪問では無理に踏み込み過ぎず
「今日はどんなふうに過ごせていますか?」と、その日の様子に寄り添うように声をかけています。
調子がいいときに頑張りすぎて、あとから気分が大きく落ち込んでしまう…
そんなケースもあるので、「ペースを保つこと」の大切さをやんわり伝えながら関わるようにしています。
認知症
精神科訪問看護では、認知症の方を担当することも少なくありません。
訪問の目的は、安心して過ごせる時間をつくること。
ご本人の様子を見守りながら、日々の生活で困っていることがないかをそっと確認します。
例えば、
- お薬の飲み忘れがないか
- 家の中で転倒などの危険がないか
など、ご本人の負担にならないよう配慮しながら見ていきます。
ご家族が同席される場面も多く、
「今日はどう過ごされていましたか?」と一緒に振り返ることで、
ちょっとした変化に気づけることもあります。
あえて、昔の話を引き出して回想法を取り入れるケースもあります。
物忘れや時間の感覚があいまいになる中でも、
「話せてよかった」と思えるような関わりを大切にしています。
不安障害
精神科訪問看護では、強い不安感や焦燥感などに悩む人と関わることもあります。
不安障害のある方にとっては「安心できる時間や会話」が支えになる場合も多い傾向です。
訪問ではまず、リラックスできる雰囲気づくりを意識。
「また同じ話をしてしまってすみません…」と恐縮されることもありますが、
その繰り返し自体が、安心を求める大事な表現の一つ。
訴えを丁寧に受け止めながら、落ち着いて話せるようなペースと声かけを心がけています。
アルコール依存症などの依存症
アルコール依存症の方では、通院や服薬を継続していくのが難しいケースも見られます。
訪問では、体調や生活リズムを確認しながら、
飲酒状況や困っていることを、無理のない範囲でそっと伺うようにしています。
中には「もう来なくていいよ」と言われることもありますが、
そうした関わりの中から少しずつ信頼関係ができていくのも、訪問看護の特徴です。
すぐに答えが出る支援ではないからこそ、
小さな変化に気づき、再発予防につなげていくことが大切だと感じています。
その他(発達障害など)
精神科訪問看護では、発達障害やひきこもり状態の方の訪問に入ることもあります。
社会との関わりがしんどくなってしまい、自宅にこもるようになった方が、訪問看護につながるケースも少なくありません。
発達障害のある方は、大人になってから生きづらさが強くなり、
「人と話すのが疲れる」
「生活を整えるのがうまくいかない」
など、日々の困りごとを抱えていることもあります。
ひきこもり状態の方も同じように、孤独や不安、生活リズムの乱れなど、それぞれの背景があります。
訪問では、まずはその方のペースを尊重し、無理のない関わりを大切にしています。
そして、小さな変化やできていることを一緒に見つけ、
「こんなふうに頑張れてますね」と言葉にすることで、少しずつ自信を育てていけるよう支援しています。
精神科訪問看護は本当にきついの?
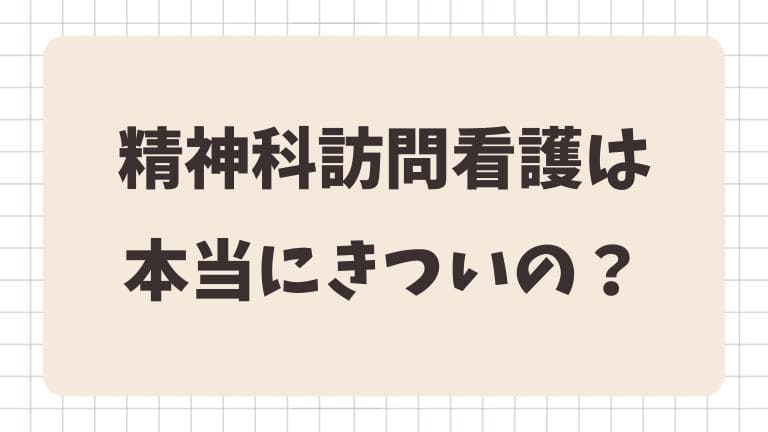
精神科訪問看護をきついと感じる原因5つ
精神科訪問看護を「きつい」と感じる原因は以下の5つが考えられます。
- 自分一人で判断したり相談対応するプレッシャーがある
- 訪問を拒否される
- 真夏の炎天下でも大雨でも自転車移動のことがある
- 対応に悩むケースに関わる負担がある
- ゴキブリがいるなど不衛生な自宅に訪問する
順番に見ていきましょう。
1.自分一人で判断や対応をするプレッシャーがある
精神科訪問看護では、一人での訪問が基本です。
慣れないうちは先輩と同行しますが、独り立ち後は単独訪問。
何か起きたとき、自分で判断・対応しなければならない場面もあります。
例えば、実際に現場で起こることもある、あくまで一例を紹介します。
- 自宅で利用者さんが倒れていた
- 高熱で寝込んでいて会話ができなかった
- 家の鍵は開いていたけど本人が不在(救急搬送されていた)
- 「今さっき転んだ」と言われ、足が腫れていた(後日骨折と判明)
頻繁ではないですが、こういった予期せぬ場面に出くわすことも。
精神症状だけでなく、全身状態の観察から、状況に応じて柔軟な対応力が求められる場面もあります。
また、利用者さんやご家族から突然、治療や介護について相談されることも。
「これは自分で答えていいのかな?主治医に確認した方がいい?」
と悩む場面もあります。
こういった“その場での判断”を迫られるのが、プレッシャーに感じる人もいるでしょう。
ただし、経験を積むうちに、できる対応・できない対応を見極めたり、上司や医師にうまくつなげたりする力は少しずつ身についていきます。
2.訪問を拒否される
精神科訪問看護では、訪問を拒否される場面も珍しくありません。
例えば、
- 「今日はいいです」「帰ってください」と言われる
- 「もう来なくていいです」と断られる
このように、その日の気分や症状によって受け入れてもらえないこともあります。
もちろん、受け入れてもらえないのはショックですし、
「次回どう関わろうか…」と悩んでしまう看護師も少なくありません。
こうした経験を「きつい」と感じる人もいます。
拒否の背景には、症状の影響がある場合もあれば、
人間同士の相性や信頼関係の構築途中であることもあります。
拒否が続くようなら、ひとりで抱え込まず、上司に相談して担当の見直しや対応方針を検討することも選択肢のひとつです。
3.真夏の炎天下でも大雨でも自転車移動のことがある
移動手段は、精神科訪問看護の“きつさ”につながることもあります。
地域や事業所の方針によって異なりますが、
- 郊外や地方では車移動が基本で、免許が必須なことが多め
- 都市部では電動自転車での訪問が中心という事業所もあり
- 「免許があれば車、なければ自転車」という柔軟な運用のところも
ただ、自転車での移動が多い職場では、
猛暑日でも大雨でも(レインコート)で自転車をこいで移動…という日もあります。
例えば、
35℃を超える真夏に汗だくで坂道を登って、
訪問先にたどり着いた頃にはもうぐったり……。
そんな日が続くと、「体力的にきついな」と感じることも出てくるかもしれません。
そのため、事前に「移動手段」についてしっかり確認しておくことは大事なポイントです。
職場選びの際に、見落としがちな部分だからこそ要チェックです。
4.対応に悩むケースに関わる負担がある
精神科訪問看護では、どう関わればいいか悩むケースもあります。
例えば、
- 内服薬に強いこだわりがあり、頻繁に処方変更を求められる
- 受診や治療を拒否し続け、最終的に自宅で看取りを迎えるようなケース
こうした場合、「どこまで医療的に関わるべきか」を本人の思いを尊重しながら、チームで話し合って決めていくことが多いです。
病棟と違って、訪問ではすぐそばに医師やスタッフがいるわけではありません。
その分、一人で判断を求められる場面が多く、プレッシャーを感じやすいという声もあります。
また、支援にはご家族やケアマネジャー、地域の他職種との連携も欠かせません。
でも実際は、話し合いが思うように進まず、調整に時間がかかることもしばしば。
「自分の力不足かも…」と感じて落ち込むこともありますが、一人で抱えず、チームで支えることが大事だと実感する場面でもあります。
5.不衛生な環境への訪問
精神科訪問看護では、掃除や片付けが難しい環境に訪問することもあります。
例えば、
- ゴミがたまって足の踏み場がない部屋
- ゴキブリなどの虫が多い部屋
- タバコの匂いがきつい部屋
など、衛生的に「つらいな…」と感じる場面もあるのが正直なところです。
精神症状の影響で、生活の管理が難しくなっている場合も多いため、
「掃除をしていない=だらしない」と一概には言えません。
とはいえ、実際に訪問する側からすると、
徐々に慣れる人もいれば、毎回こうした環境に入るのは少なからず負担、
という声も聞かれます。
マスクや手袋、シューカバー、アルコールなどを持参して工夫しながら対応しますが、
精神科訪問看護の現場で覚悟しておきたい一面です。
精神科訪問看護をきついと感じやすい人の特徴5つ
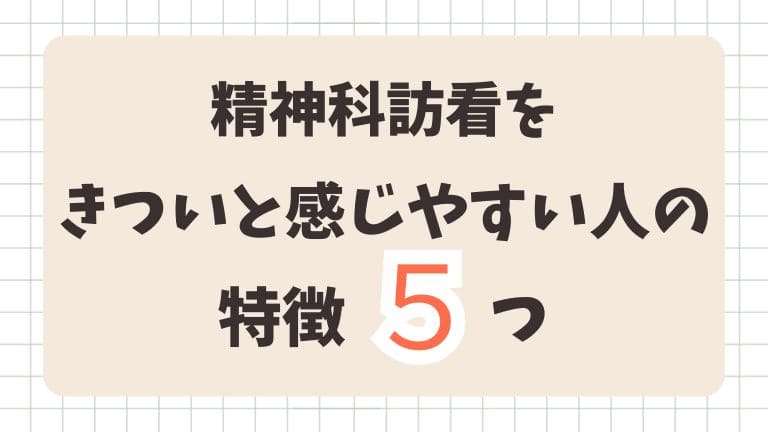
精神科訪問看護をきついと感じるかどうかは、本当に人それぞれです。
精神科訪問看護が「きついな」と感じやすい方の特徴には、以下のような傾向があります。
- 一人で判断するのが苦手な人
- 想定外の出来事に強いストレスを感じる人
- 距離感のとり方に悩みやすい人
- 臨機応変な対応が極端に苦手な人
- 清潔な環境でのケアが絶対条件な人
訪問看護では、利用者さんの生活空間に入って支援するため、
ある程度の柔軟さや、対応力が求められます。
もちろん、最初から完璧じゃなくてOK。
でも
「一人で動くのが不安」
「曖昧な状況が苦手」
と強く感じる場合、
きついと感じやすい傾向があるかもしれません。
ただ、こうしたことはあくまで傾向です。
逆に、
- 誰かの話をじっくり聴いたり
- 状況を見ながら考えるのが得意な人
には、大きなやりがいや喜びを感じられる仕事でもあります。
精神科訪問看護をきついと感じる時の対処法4つ
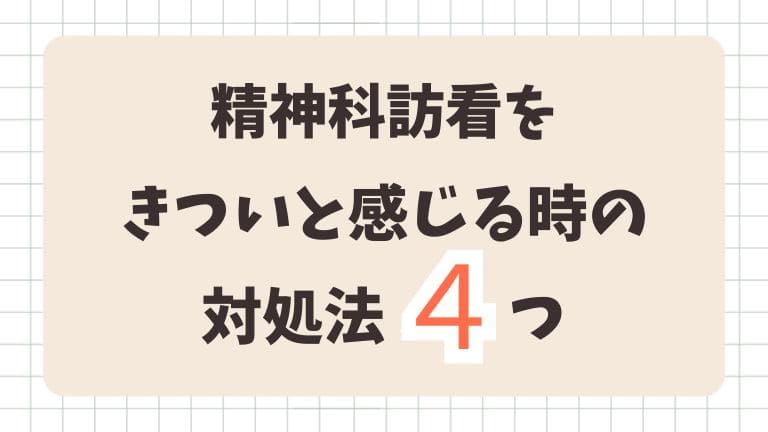
精神科訪問看護は、やりがいのある仕事ですが、ときには「しんどいな…」と思う瞬間もあります。
そんなときは、無理をしすぎず、次のような対処法を意識してみて下さい。
- 一人で抱え込まず先輩や上司に話してみる
- 訪問中に判断に迷ったら上司に指示を仰ぐ
- 小さなことでも「できたこと」を振り返る
- 相性が合わなければ担当を変えるのも一つ
1.一人で抱え込まず先輩や上司に話してみる
訪問のあと、「この対応でよかったのかな?」とモヤモヤすること、ありますよね。
そんなときは、悩みをひとりで抱え込まず、周りに話すことも大切です。
信頼できる先輩や上司に話すと、「それで大丈夫だよ」と軽く言ってもらえるだけで、気持ちが楽になることもあります。
同じような経験をしている人に相談することで、新たな視点や安心感が得られることも多いです。
2.訪問中に判断に迷ったら上司に指示を仰ぐ
状況にもよりますが、訪問中に迷ったら、すぐにひとりで決めようとしなくてOKです。
状況によっては、その場で上司に連絡して、アドバイスをもらうのが安心。
「困ったら連絡して大丈夫」と思えるだけで、気持ちに余裕が出てきます。
3.小さなことでも「できたこと」を振り返る
上手くいかない時でも、小さな「できたこと」「今できていること」を振り返るのはおすすめです。
訪問の仕事は、一回で劇的に変化が出るものではありません。
だからこそ、
- 「今日は落ち着いて話を聞けた」
- 「薬の確認をスムーズにできた」
- 「適切なタイミングで上司に相談できた」
など、小さな“できたこと”を振り返るだけでも、気持ちがスッと軽くなります。
少しずつ関係を築いていけている――
その実感が、次の訪問への自信につながっていきます。
少しずつでも成長している自分を認めてあげて下さい。
4.相性が合わなければ担当を変えるのも一つ
利用者さんとの相性が合わずに拒否され続けている場合、担当を変えるのも一つの選択肢です。
利用者さんに訪問を拒否されると、「自分がダメだったのかな…」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
でも実際には、
- 気分や症状の波
- 相性の問題
- 訪問看護の必要性を感じていない
など、いろんな理由が重なってうまくいかないこともあります。
そんなときは、一人で悩まず上司やチームに相談して、担当変更を含めた対応を考えてみるのも一つの方法です。
自分を責めすぎず、周囲と相談しながら、できることから少しずつ整えていく姿勢が大切です。
きついって本当?訪問看護未経験から転職した体験談
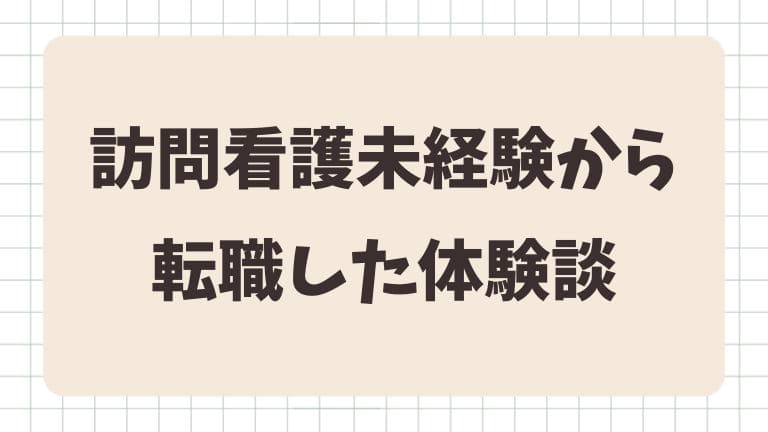

実際働いていて、きついと感じたのはどんな時でしたか?

訪問看護未経験から転職して、私が一番きついと感じたのは
「あまり訪問を望んでいない方」のところへ伺った時でした。

具体的にはどんな感じだったのでしょうか?

毎回、話しかけても反応がそっけなかったり、
「早く帰ってほしいのかな…」と感じるような空気がありました。
やっぱりちょっと切なくなったり「自分は必要とされていないのかも」と不安になることもありました。

きついと感じた時はどう対処したのですか?

私の場合は、働く中で少しずつ考え方が変わっていきました。
- 精神科看護は、会話だけがすべてではないこと
- 拒否されるかどうかよりも、その人が穏やかに過ごせているかどうかに目を向けてみること
- 本当に訪問が負担なら、主治医に相談して中止を希望される方も多い印象。
でも、そうされていないなら「訪問を受けること」にどこか意味を感じてくれているのかもしれないこと - 長く関わる中で「何かあったらちょっと聞いてみようかな」と思ってもらえる存在を目指すこと
こうした考えを持てるようになってからは、少しだけ肩の力が抜けて、訪問が前よりも楽になりました。

もちろん今でも悩むことはあります。
でも、長く関わる中でぽつりと悩みを話してくれた時は「この仕事を続けていてよかった」と思える瞬間です。
精神科訪問看護ならではの難しさはありますが、それ以上にやりがいもある仕事だと、今では感じています。
精神科訪問看護の1日の流れとスケジュール
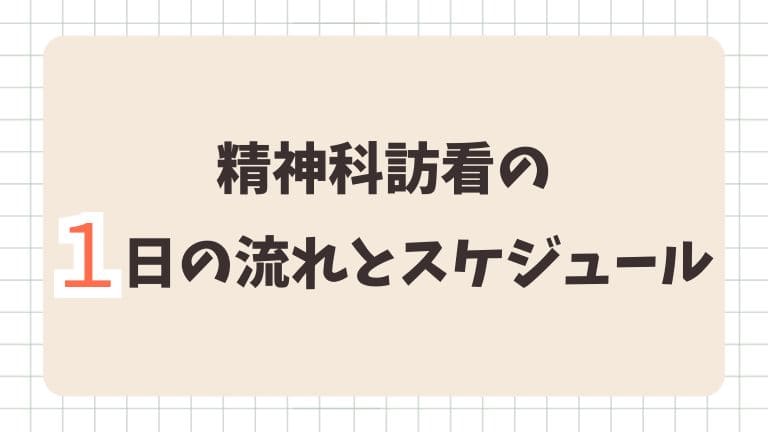
精神科訪問看護の1日の流れとスケジュールについて紹介します。
※一例なので、時期や対応地域によって異なります
9:00 始業・情報収集
- 当日の訪問予定を確認
- 前回訪問からの状態変化を電子カルテで確認
- 必要な資材や書類を準備
準備を終えたら訪問に出発!
9:30 午前の訪問スタート
- 午前中は2〜3件訪問(1件あたり30分〜1時間程度)
【訪問先で行うこと】
- バイタルチェック
- 服薬管理
- 精神状態・身体状況の観察
- 必要時、ご家族にお話を伺う など
終了次第、事業所に戻る
12:00 事業所に戻ってお昼休憩
- 12:00〜13:00休憩・昼食(事業所によっては、外食OKの場合もあり)
- 午前の訪問内容を記録
- 午後の準備を整えつつ休憩
準備ができたら訪問先に出発!
13:00 午後の訪問開始
- 午後は3〜5件訪問
- 症状が不安定な方や、ゆっくり話をする時間が必要な方の場合は訪問が長めになることも
終了次第、事業所に戻る
17:00 事業所に戻って記録・情報共有
- 午後の訪問内容を電子カルテに記録
- 必要に応じてケアマネジャーや主治医へ報告
17:30 ミーティング
- 職員全員で事務連絡や共有事項
- 本日の訪問で、状態不安定な人・気になる状態の人を職員で共有
【ミーティング後】
- 本日の訪問の記録
- 翌日の準備
- 事業所の掃除
18:00 退勤
- 緊急対応などがなければ、定時で退勤。
精神科訪問看護の業務内容でよくある質問
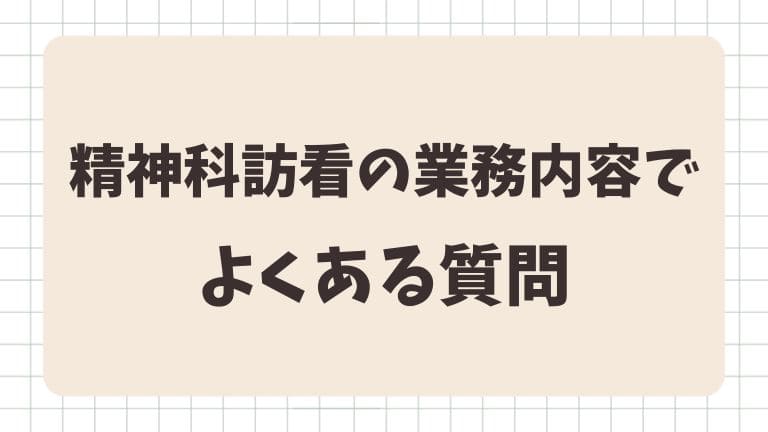
准看でも精神科訪問看護で働ける?
准看護師でも精神科訪問看護ステーションで働くことは可能です。
多くの事業所で、精神科訪問看護ステーションの准看護師の求人もあります。
ただし求人によっては
- 「精神科経験1年以上」
- 「研修修了」
といった条件がつくことが多いので、応募前に確認しておくと安心です。
未経験から入職し、研修を受けて経験を積むケースもあります。
精神科訪問看護はパートの求人もある?
精神科訪問看護にはパートやアルバイトの求人もたくさんあります。
- 勤務日数
- 勤務時間
が相談できる職場が多く、週2〜3日からや、短時間から働ける求人も多数あります。
ライフスタイルに合わせて働きやすいのが特徴で、パート勤務でも選択肢が豊富です。
「少しずつ訪問看護に慣れたい」という方にもおすすめです。

フルタイムは難しいけど少しだけ働きたい人にもピッタリ!
精神科訪問看護でしてはいけないことは?
精神科訪問看護では、次のような点には特に気をつけています。
- 症状に影響するような対応は慎重に
- プライバシーへの配慮も忘れない
- 自己判断で医療的な対応をしない
症状に影響するような対応は慎重に
ちょっとした言葉がきっかけで、気分や体調が不安定になる方もいます。
だからこそ「この言い方で大丈夫かな?」と考えながら、できるだけ安心できる関わり方を心がけることが大切です。
プライバシーへの配慮を忘れずに
訪問ではご近所の目もある中での対応になることがあります。
インターホンでの声かけや会話の内容など、周囲に配慮しながら失礼のない対応を意識しています。
自己判断で医療的な対応はしない
訪問中に体調が気になることがあっても、自分だけで判断せず、必要に応じて主治医や事業所内で相談するようにしています。
「ひとりで背負い込まない」ことが、結果的に利用者さんの安心にもつながります。
※この記事は、実際の訪問現場での経験をもとに記載しています。
医療的な判断が必要な場合は、主治医や専門職にご相談ください。
【まとめ】精神科訪問看護の仕事を知ろう!
精神科訪問看護は、バイタルや服薬管理だけでなく、精神状態の観察やご家族の支援など、一人ひとりにじっくり寄り添うケアが求められます。
その分「きつい」と感じる場面もありますが、それ以上に利用者さんの小さな変化や言葉に大きなやりがいを感じられる場面も多い分野。
未経験やブランクがあっても挑戦できる職場はたくさんありますし、短時間勤務やパートで少しずつ慣れていく方法もあります。
もし少しでも興味を持ったなら、まずは求人を見てみるところから始めてみてください。
あなたに合った働き方や、訪問ならではの魅力に出会えるかもしれません。
